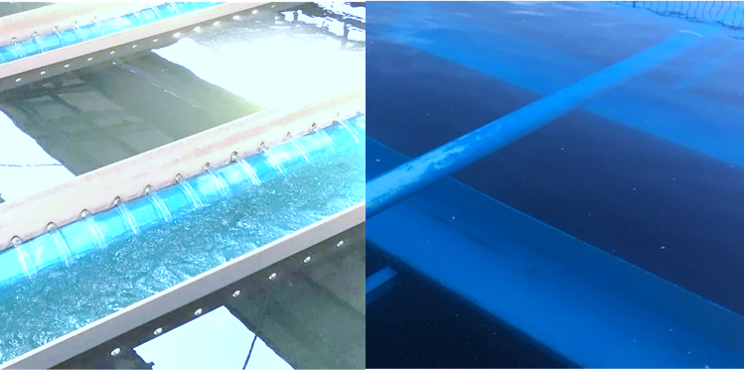浄水場の設計の基本事項について
水道施設設計指針(公益社団法人 日本水道協会)に基づき、一般的な凝集沈殿急速ろ過方式(図1)の各施設について取り上げ、基本的な考え方や設計に関わる数値等を整理してみました。
(技術士:上下水道部門 一次試験、二次試験向け)
図1 急速ろ過方式の浄水フロー図
1.計画浄水量
・計画浄水量は、計画一日最大給水量を基準とし、これに作業用水などを見込んで決める。
(作業用水としては、沈澱池の排泥、ろ過池の洗浄用水又は洗砂用水、水質試験用水及び施設の清掃用水などがあり、雑用水としては、場内給水、場内清掃用水等がある。)
・浄水場内の施設を複数の系列に分割する場合、浄水場の予備力は、その一系列相当分とし、当該浄水場の計画浄水量の25%程度を標準とする。
2.浄水場の配置
急速ろ過方式の浄水施設の配置について留意すべきポイントを施設別にあげると以下のとおりである。
(1) 着水井
着水井は、その後の凝集、沈澱、急速ろ過と続く処理工程をスムーズに行える位置に選定する。
(2) 凝集池、フロック形成池及び沈澱池
凝集池、フロック形成池及び沈澱池は、連続した処理工程なので、それぞれを分離して配置することは好ましくない。分離すると距離が長くなり、流下時間が長くなって良好なフロックの成長を妨げたり、水路の途中でフロックの沈澱が生じたりする。
(3) 急速ろ過池
急速ろ過池は、ろ過水管、流入管、逆流洗浄管等多数の管を集めて配置することになるので、管廊を設けて付属施設をまとめ、配管の連絡及び弁類や流量調節装置の設置が容易なものとする。
(4) 消毒
消毒は、ろ過水が集合した所に混和渠を設けて塩素剤の注入を行う。ろ過後は、汚染を避けるために密閉した構造とすることが原則であるので、通常、混和渠(後塩素の混和:塩素混和池)はろ過水が浄水池に行くまでの間の浄水渠の一部を利用することが多い。
(5) 浄水池
浄水池は、水位的に低い位置となるので、地下構造となることが多い。上部の空間はろ過池を配置して立体構造として利用されることもある。
(6) 着水井から浄水池までの配置
着水井から浄水池までは通常自然流下で連絡するので、連絡管や水路をなるべく短くして損失水頭の軽減を図る。用地の制約上、これらを近接して配置できない場合には、凝集池から沈澱池まではなるべく一つにまとめ、ろ過池と浄水池はやや離れた所に配置することもある。急速ろ過方式の場合、高度浄水処理などを行わない通常の凝集・沈澱・ろ過の施設全体での損失水頭は3.0~5.5m程度である。(図1:急速ろ過方式のフロー図で示すところの着水井~浄水池で3.0~5.5m水位が下がる)
損失水頭の大部分はろ過池の損失水頭である。その他はフロック形成池や管路及び水路、渠などの抵抗、流量制御の弁・ゲートの損失などである。
3.着水井の設計
・着水井の滞留時間は1.5 分以上とし、水深は3.0~5.0mとする。
・着水井は、原則として二つ以上に分割し、各々に排水設備を設ける。
・着水井の水位が高水位以上にならないよう、越流設備など必要な措置を講じる。
・着水井で注入する薬品としては前塩素、pH調整剤(希硫酸、苛性ソーダなど)がある。
4.急速撹拌池(急速混和池)の設計
・凝集剤の注入場所は原則として急速撹拌池(急速混和池)とする。
・水流が共回り運動を起こしたり、短絡流を生じたりしない構造とする。
・凝集剤を注入したあと、直ちに急速な撹拌を与え、凝集剤を原水中に均一に拡散させることのできる適切な混和装置(急速撹拌装置:フラッシュミキサー)を設ける。
・混和時間は、撹拌強度にもよるが計画浄水量に対して1~5分間を標準とする。
・凝集剤の注入量は、処理水量と注入率から算出する。
・凝集剤はジャーテストによる実験を行い、注入率範囲(最高、最低及び平均)を決める。
・浄水処理及び薬品管理の容易さから、凝集剤は一般的にポリ塩化アルミニウム(PAC)を使用する所が多い。適用pH 値範囲が広く、アルカリ度の低下量も少ないなどの特微がある。
5.フロック形成池の設計
・短絡流や停滞の生じないような構造とし、またスラッジやスカムを除去できるような設備を設ける。
・設置場所は、混和池(急速撹拌池)と沈澱池の間とし、それらと一体構造として設ける。
・形状は、長方形を標準とし、機械式あるいは迂流式の撹拌装置を設ける。
・滞留時間は、計画浄水量の20~40 分間を標準とする。
・撹拌装置(緩速撹拌装置:フロキュレータ)の周辺速度は15~80cm/s、迂流方式の場合の平均流速は15~30cm/sを標準とする。
・下流に行くに従って、撹拌強度を漸減する。(テーパード・フロキュレーション方式)
・撹拌の強度を調節できるものとする。
6.凝集沈殿池(薬品沈殿池)の設計
・必要に応じ覆蓋設備を設ける。
・池数は、原則として2池以上とする。
・各々の沈澱池に水を均等に流出入させるように配置する。
・各池ごとに独立して使用可能な構造とする。
・形状は長方形とし、沈澱部の長さは幅の3 ~8倍を標準とする。
・有効水深は3~4m程度とし、堆泥深さとして30cm 以上を見込む。
・高水位から沈澱池天端までの余裕高は、30cm を標準とする。
・池底には排泥に便利なように、排水口に向かって勾配をつける。
<横流式沈澱池>
・池内の平均流速は、0.4m/min 以下を標準とする。
・表面負荷率は、 単層式沈澱池15~30mm/min 、多階層式沈澱池15~25mm/min とする。
<傾斜板(管)式の沈澱池>
・藻類の繁茂による障害対策を講じる。
・沈澱池の形式等を考慮して、傾斜板等の沈降装置の種類・形式等を定める。
・傾斜板等の沈降装置への流入を均等にし、短絡流を防止するための有効な措置を講ずる。
・水平流式の傾斜板等の沈降装置を設置する場合(図1:急速ろ過方式のフロー図に相当)
表面負荷率は、4~9mm/min とする。
装置の傾斜角は、60°とする。
池内の平均流速は、0.6m/min 以下とする。
装置の下端と池底との間隔は、1.5m以上とする。
装置の端と沈澱池の流入部壁及び流出部壁との間隔は、それぞれ1.5m以上とする。
・上向流式の傾斜板等の沈降装置を設置する場合
表面負荷率は、7~14mm/min とする。
装置の段数は、1段とする。
装置の傾斜角は、60°とする。
池内の平均上昇流速は、80mm/min 以下とする。
装置の下端と池底との間隔は、1.5m以上とする。
装置の端と流入部壁との間隔は、1.5m以上とする。
装置下部の入口における平均流速は、0.7m/min 以下とする。
・傾斜板等の沈降装置は、地震等によって破損することがないよう適切な装置を講じる。
7.急速ろ過池の設計
・形状は、長方形を標準とする。(おむね5:1以下を目安とする。)
・ろ過面積は、計画浄水量をろ過速度で除して求める。
・池数は、予備を含め最小限2池以上とし、予備池は10 池までごとに1池の割合とする。
・1池のろ過面積は、150㎡以下を標準とする。
・急速ろ過池には、ろ過流量を調節する機構を備える。
・ろ過速度は、120~150m/日が一般的である。
・ろ過砂は、粒度分布が適切で、夾雑物が少なく、摩耗しにくく、衛生上支障のないもので、ろ過及び洗浄を安定して効率よく行うことができるものとする。
・砂層の厚さは、60~70cm を標準とする。
・ろ過砂利の粒径と砂利層の厚さは、下部集水装置に合わせて適切に決める。
・下部集水装置は、均等かつ有効なろ過と洗浄ができる構造とする。
・ろ層の洗浄は、逆流洗浄に表面洗浄を組み合わせた方式を標準とし、ろ層が効率よく洗浄できるものとする。また、必要に応じて逆流洗浄と空気洗浄を組み合わせたものにする。
・洗浄に必要な水量及び時間は十分な洗浄効果が得られるものとする。
・洗浄には、浄水を用いる。
・急速ろ過池~浄水池の間に塩素混和池を設けて、後塩素を注入することが多い。
8.浄水池の設計
・構造的に耐震性、耐久性を十分保ち、衛生的に安全で、かつ水密性を有するものとする。
・池数は、原則として2池以上とする。
・高水位から上床版まで30cm 程度の余裕高をとる。
・低床版は低水位より15cm 以上低くする。
・低床版は必要に応じて排水のための勾配をつける。
・地下水位の高い場所や砂質地盤、埋立地等に築造する場合は、沈下、浮き上がり等を防止する対策を講じる。
・寒冷地において、水温保持の必要がある場合は、適当な対策を講じる。
・最高水位は、施設全体としての水理条件により決定する。
・有効水深は3~6m程度を標準とする。
・浄水池の有効容量は、計画浄水量の1時間分以上とする。
浄水場を見学して実際の水の流れや動いている設備を見るととても勉強になるのでおススメです!